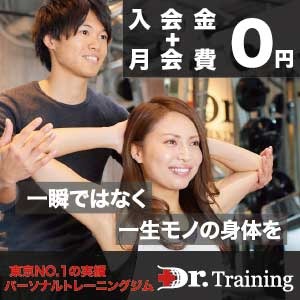コチラの記事はその①からの継続です。
まだその①を読んでいない方はぜひそちらの是非からどうぞ!
記事は コチラ です!
--続き--
明らかな違いは何だったのか?
さて、自分なりに中厚系ラケットと薄ラケットで何が違うのかを考えてみました。
自分の中では一番の違いは「アシスト性能」だと思います。
中厚系のラケットはアシストをコントロールするのは困難だと思ったからちょっと試してみようと思った薄ラケットがドンピシャだったという点を考察してみると・・・
中厚系のコントロール不能感、飛びすぎる、の正体
中厚保系のラケットでは10でスイングすると10のアシストを得られて20のパワー(飛び)が得られるとします。
それをコートに納めるためにスピンをかけなければならず、スピンの意識強めの下から上へのスイングをしていました。で、さらにすこしショートクロス気味やストレートへ打つのに上記の合計20のパワー(飛び)をスピンで納めるにはものすごいスピンが必要でそれは自分には無理でした。
なのでそういったボールを打つには自分が6のパワーで打って、ラケットのパワーアシスト5を得て11のパワー(飛び)を得て、それをスピンでコントロールする、というのが自分のやりかたでした。
ここで問題なのが、自分はパワーを10→7にしても得られるラケットアシストは10→5になる。このラケットアシストのコントロールが困難だと素人のぼくは感じました。得られた合計にパワー(飛び)をスピンで納めなきゃならない、そのスピンの量のコントロールもしなきゃならない、となると自分が制御しなければならないものが多くて複雑・・・でした。
逆なこともあって自分は7→10のパワーで打ちますがラケットアシストは5→10得られて合計のパワー(飛び)は12→20まで変化する。これを感覚的に飛びすぎ、と感じるのではないでしょうか?
自分で自分の打つボールをコントロールできる!
今のラケットに変えて何が変わったかというと、この「ラケットアシストによる誤差」が小さくなったといえます。
自分のスイング10の時の今のラケットのアシストはおそらく5くらいです。合計15のパワー(飛び)が得られます。
で、スイングを7にするとラケットによるアシストは3くらいです。合計で10の パワー(飛び)を得られます。
このくらいのラケットアシストの誤差ならコントロールできる、自分のスピンでも制御が可能、すなわち自分にとってコントロール性能が高い、ということになります。ということです。
さらに良い誤算もあって、ショートアングルやストレートを打つ時、自分のスイングを7にしなくても、10のスイングでラケットアシストが5なら、合計は15の パワー(飛び)を得られますが、この15なら、スピンのコントロールで深くも浅くもできる、という自分のスピンでほぼコントロールできる、ということがわかりました。これがすっごくハマっています。
図式にするとこんな感じ?
自分の力 ラケットアシスト 合計(飛び)
中厚系 10 10 20
7 5 12
※自分の力を10→7にしても合計の飛びは「8」も違う
薄ラケ 10 5 15
7 3 12
※自分の力を10→7にしても合計の飛びは「3」しか違わない
何故プロは使ってる(゜〇゜;)
じゃあなぜプロはアシストの強い飛ぶラケットを使うのか、という点については「それ以上のスピンをかける能力があるから」だと思います。プロでもBabolatさんのピュアドライブをはじめ、どんなに「飛び」の性能が高いラケットでも素人の2倍、3倍、10倍のスピンをかけてコントロールすることができるから、だと思います。
その分プロは1試合のプレー時間が長いので、楽をして飛ばせるラケットの方が身体的には楽、という事では無いかなと思います。
これはラウンド形状とボックス形状にも同じことが言えるかもしれません!僕が今使っているPrinceさんのPHANTOM100(2019年モデル)は薄ラケですがストリングパターン16×18だし、ラウンド形状なのでそこまでしんどいラケットではない、というのもあります。
とにかくテニスラケットは奥が深い・・・
これからもっとたくさんのラケットを打ってたくさんインプレしていきたいですね!頑張ります!